姿勢矯正するならjsメディカルへ!
食中毒は統計的にも年間の中で6月が多く、食中毒の原因は細菌(バクテリア)やウイルス、寄生虫などです。6月は湿度や気温が高くなるので、細菌が増殖しやすく、細菌性の食中毒の発生件数が増える傾向にあります。細菌性というのは、具体的には、カンピロバクターやブドウ球菌、ウェルシュ菌などです。例えば、カンピロバクターは、鶏肉の加熱不足などが原因。ブドウ球菌は、おにぎりや弁当の不衛生が原因、ウェルシュ菌は、前日のカレーやシチューをそのまま置いていた場合が原因です。
いずれの菌も湿気が多く気温の高い梅雨どきに活動を活発化させて、下痢、腹痛、おう吐、発熱などが現れます。
食中毒の一般的な症状は、下痢、腹痛、おう吐、発熱などです。特有の症状はないので、風邪などに間違われることもよくあります。ただ、食事後数時間してからこうした症状が起きた場合は、食中毒を疑う必要があります。「食中毒かな」と思ったら、下痢やおう吐で水分を喪失するので、脱水症状を起こさないように、水分補給をこまめにすることが重要です。
食中毒の予防は、細菌を食べ物に「付けない」、「増やさない」、「やっつける」という三原則となります。細菌を付けないためには、手洗いが大切です。細菌を増やさないための基本は低温での保存です。つまり冷蔵庫。細菌をやっつけるには、加熱処理です。ほとんどの細菌は加熱によって死滅しますので、十分加熱して食べれば安心です。




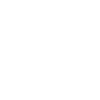 ポスト
ポスト
 シェア
シェア




